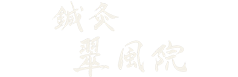2025/09/20
起立性調節障害と東洋医学 ~鍼灸翠風院の考え方+エビデンス~

思春期のお子さんや若い方で、「朝、起きられない/立つとめまいや動悸がする/午前中が特につらい」などの症状でお悩みのケースが増えています。これは「起立性調節障害(orthostatic dysregulation, OD)」と呼ばれる、自律神経の調節機能の不具合に基づく状態です。以下では、まず西洋医学側の知見を整理し、それを東洋医学/鍼灸視点でどう捉えるか、また鍼灸でどこまで期待できるか、最新の情報を交えてお伝えします。
西洋医学でわかっていること
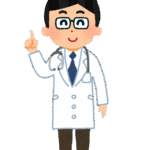
まず、ODについて医学的な基礎を整理します。
-
起立性調節障害は、立ち上がったときの血圧・心拍などの循環動態を体がうまく調整できないことで、立ちくらみ、めまい、動悸、起床困難、午前中の体調不良などを引き起こします。 J-STAGE
-
症状がひどくなると、登校障害や社会生活への影響も出ることが報告されています。 J-STAGE
-
治療としては、まずは生活指導(起床時の方法、睡眠・光環境・栄養・水分/塩分の摂取など)や運動療法、食事療法が基本。その上で、症状が中等度以上か改善が見られない場合には薬物療法が併用されることがあります。 J-STAGE
東洋医学的視点:体質と病態の捉え方
鍼灸翠風院としては、ODの症状・背景を以下のような東洋医学(中医学)語で整理すると理解しやすく、治療方針の立てやすさも増します。
| 東洋医学用語 | 意味/特徴 | ODにおける関係例 |
|---|---|---|
| 気虚(ききょ) | 生命エネルギー=「気」が不足している状態。「疲れやすい、朝起きにくい、活動力低下」など | ODの起床困難、午前中のだるさ、疲労感につながる |
| 血虚(けっきょ) | 血の栄養・潤いが足りない状態。「貧血傾向、顔色不良、動悸、息切れ、不眠」など | 動悸・めまい・顔色の悪さ・睡眠の質低下などで見られることがある |
| 気血両虚(きけつりょうきょ) | 気虚と血虚の併存。両方の不足により症状が複雑・重くなる | ODで複数症状(起床困難+めまい+食欲不振など)があるケースで該当しやすい |
| 気滞(きたい) | 気の巡りが滞る、流れが悪くなる状態。「胸や腹の張り、イライラ、不安、吐き気」など | ODのストレスや生活不規則から二次的に起こることが多い |
| 水滞(すいたい) | 体液の代謝が滞り、むくみ・冷え・重だるさなどが出る状態 | ODで冷えや四肢の冷たさ、体液バランスの問題が見られる場合に関与すると考えられる |
このような体質傾向を見極めることが、東洋医学的な施術を行ううえでの出発点です。
複数の情報源で、ODに気虚・血虚・気滞・水滞などの東洋医学的分類が使われており、漢方薬処方例も多数報告されています。 123do.co.jp+2yoshi-ent.jp+2
鍼灸治療で期待できることと実例
鍼灸翠風院としては、東洋医学の診断を元に「体全体のバランス調整」「自律神経の安定」「気・血・水の巡りの改善」を目指します。
鍼灸での治療メカニズム(東洋医学+現代医学的見方)
-
鍼灸によって自律神経(交感神経と副交感神経)のバランス(陰陽)を整える刺激が入る → 血圧/心拍/末梢血管の反応性改善の可能性あり。
-
気虚・血虚の補填を助けることで、体の基本的な回復力が上がる。基礎体力が向上。
-
気滞・水滞のような滞りを改善することで、むくみ、冷え、凝り、ストレス関連の症状を和らげる。
実例:鍼灸によるOD改善の報告
代表的な報告として、
-
「起立性調節障害に対する鍼灸治療の1症例」(佐藤美和・福島正也、2019)という論文があります。14歳の男児で、薬物療法では十分改善がみられなかった症例です。鍼灸を16回実施したところ、遅刻・欠席・起床困難等の症状が著しく改善しました。 J-STAGE+1
-
また、漢方を含めた東洋医学的処置で、気虚・血虚・水滞の改善が見られ、学校生活や社会生活の質が上がったという報告もあります。 natsume-pharma.com
当院でも起立性調節障害の症例は数例あり、回数に違いはありますがQOL向上や生活の改善から社会(学校)復帰出来た例があります。
今後症例に追加予定です。
これらは「症例報告」であり、大規模な臨床試験による強い証明(エビデンス)ではありませんが、現場での改善例として参考になるものです。
鍼灸翠風院での治療方針例
翠風院では、上のような東洋医学的/西洋医学的情報を踏まえて、以下のような方針で治療を組み立てます。
-
初診時の体質診断
問診で症状の時間帯・生活リズム・ストレス・冷え・食欲・睡眠などを詳しくうかがい、気虚か血虚か、気滞あるいは水滞などの判別に加え、臓腑経絡のアンバランスの有無を判断します。 -
鍼灸施術
- 気を補うツボ(例:脾経関連のツボ)
- 血を補う・巡らせるツボ(例:肝経のツボ、三陰交また背部兪など)
- 自律神経を整えるツボ(百会、後溪など)
- 冷えがきつい(陽虚)の場合は必要に応じてお灸をを行う。 -
生活・養生アドバイス
- 朝の光を浴びること(自然光)
- 起床時の動作をゆっくりする(ベッドでの準備運動など)
- 食事内容:脾胃を助けるもの、栄養のバランスをとるもの
- 睡眠環境の改善(画面の光、就寝時間の安定など) -
漢方薬併用の検討
体質によっては漢方薬(気虚を補う、生薬で血を補う・巡らせるものなど)を併用することもあります。実際、多くの漢方薬処方例が報告されており、ツボ中心の鍼灸と漢方の併用は東洋医学的に理にかなっています。 一般社団法人 起立性調節障害改善協会+2123do.co.jp+2
注意点と限界
鍼灸翠風院としてお伝えしたいのは、次のような注意点です。
-
鍼灸は万能ではありません。症状の重さや持続時間、他の疾患合併の有無などにより、反応が異なります。
-
西洋医学の検査も重要です。特に起立テスト、心電図、血圧測定等で重篤な異常や危険因子がないか確認することが大前提です。
-
漢方薬・薬・サプリメント等との併用・相互作用に注意すること。医師との連携があると安心です。
-
エビデンス(科学的根拠)がまだ豊富とは言えない領域です。症例報告などはあるものの、ランダム化比較試験などの規模の大きい研究はこれからの進展が期待されます。鍼灸師・漢方医・小児科医などの協力が重要です。 jptoho.or.jp+1
結びに ‐ 鍼灸翠風院から皆さまへ

起立性調節障害は「甘え」でも「怠け」でもなく、体の「調整機能」のアンバランスによって引き起こされるものです。東洋医学では、このアンバランスを“気・血・水・陰陽・気の流れ”などの概念で捉え、体全体を整えることで「自然に動ける・朝起きやすい・めまいが少ない」状態を目指します。
鍼灸翠風院では、一人ひとり違う体質を丁寧に診てご提案を差し上げています。もし「朝が怖い」「体がだるくて学校に行けない」と感じる日々が続いていたら、一度お気軽にご相談ください。東洋医学の視点で、あなた/お子さんに本当に合った調整をお手伝いしたいと考えています。