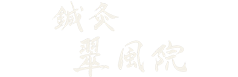【症例集】頭痛
- HOME
- 【症例集】頭痛
三宮 頭痛 鍼灸|神戸の鍼灸 翠風院 症例と東洋医学的解説
三宮 鍼灸 頭痛・片頭痛・緊張型頭痛・自律神経・気象病・ストレス・東洋医学
「病院で異常がないと言われた」「薬に頼らず整えたい」「雨の日に必ず痛くなる」―― 鍼灸 翠風院では、頭痛を“全身の乱れのサイン”として捉え、身体の内側から静かに整えていく施術を行っています。
頭痛とは ― 西洋医学と東洋医学の両面から
西洋医学では、頭痛は大きく「一次性頭痛」と「二次性頭痛」に分類されます。 一次性頭痛には片頭痛・緊張型頭痛・群発頭痛などがあり、二次性頭痛は脳出血や感染症など別の病気が原因で起こるものです。 多くの方が悩む慢性頭痛は一次性に属し、ストレス・自律神経の乱れ・睡眠不足・天候の変化などが引き金となります。
東洋医学では、頭痛は「頭の気血が滞り、陽気が上衝する」ことで生じると考えます。 特に肝・脾・腎の働きの不均衡が深く関係しており、気圧や気温の変化、情緒の乱れ、体内の冷え・湿気が原因で起こることが多いとされます。 単なる痛みではなく、身体全体のバランスの乱れが「頭」という最も敏感な部分に現れた状態なのです。
頭痛の一般的な医学情報:第一三共ヘルスケア「頭痛について」
実際の症例紹介
【症例1:60代女性/緊張型頭痛と片頭痛の混合型】
主訴:慢性的な頭痛、胃もたれ、肩こり、膝痛
現病歴:20代後半から頭痛が始まり、締めつけられるような痛みとズキズキとした拍動痛が交互に出現。 痛みが強いと嘔吐を伴い、救急搬送歴もあり。特に雨の前に悪化し、鎮痛薬が手放せない状態。 胃の不調・肩こり・膝痛も併発していたため、体全体の調整を希望して来院。
施術経過:月3〜4回、足の経穴を中心に1〜2本の鍼を使用。気血の巡りを整え、体の冷えを温めながら施術を継続。 3か月で頭痛の頻度が半減し、1年経過時には痛み止めを使用せず過ごせるようになる。 現在も季節の変わり目に軽度の頭痛が出る程度で、定期的に体調維持の施術を継続中。

※症例は施術の一例であり、すべての方に同様の結果を保証するものではありません。 症状・体質・生活習慣により経過は異なります。
ご予約・ご相談はこちらから
頭痛でお困りの方、薬に頼らず整えたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談はLINEで無料受付中です。完全予約制の静かな個室空間で、安心してお過ごしいただけます。
頭痛と東洋医学 ― 深い理解と整え方
東洋医学における頭痛の理解は、非常に奥深いものです。 単なる「脳の問題」ではなく、全身のエネルギー循環・内臓の働き・精神的な緊張などが複雑に絡み合って生じる現象と考えます。 そのため、「どの臓腑が乱れているか」「どの経絡に滞りがあるか」を見極めることが、治療の鍵となります。
1. 肝(かん)と気の上衝 ― イライラや緊張で起こる頭痛
肝は「気の流れ」を司る臓で、ストレスや怒りなどの感情が強いと気が上昇し、頭に熱をこもらせます。 これを肝陽上亢(かんようじょうこう)といい、こめかみや頭頂部にズキズキする痛み、目の充血、顔のほてりを伴います。 東洋医学では、百会・太衝・風池などのツボを使い、上昇した気を穏やかに下げていきます。
2. 脾(ひ)と湿 ― 天候や食生活が関係する頭重感
雨の日や梅雨時に頭が重くなる方は、体内に「湿(しつ)」がたまりやすい傾向があります。 冷たい飲食物・不規則な食事・胃腸の疲れが原因で、水分代謝が滞り、頭部に重だるさを感じやすくなります。 これは脾虚湿困(ひきょしつこん)と呼ばれ、足三里・豊隆・陰陵泉などで脾の働きを助け、体内の余分な湿を排出していきます。
3. 腎(じん)と精 ― 慢性疲労や加齢に伴う後頭部の鈍痛
腎は生命力の源であり、加齢や疲労で腎の気が弱ると、頭を支える力が不足し、 後頭部や首の付け根が重く痛むようになります。 このタイプは冷えや倦怠感を伴うことが多く、命門・腎兪・太谿などを温めながら施灸することで、深部のエネルギーを回復させていきます。
4. 気滞血瘀(きたいけつお)型 ― 血流の滞りによる刺すような痛み
長時間のデスクワークや眼精疲労、姿勢の悪さなどで気血が滞ると、血瘀(けつお)と呼ばれる状態になります。 鈍痛ではなく、刺すような鋭い痛みや頭の一点に集中する痛みが特徴です。 鍼灸では、風池・天柱・肩井・合谷などを用い、首肩から頭部への血流を回復させます。
5. 陰陽のバランスを整える ― 鍼灸がもたらす調和
東洋医学における鍼灸の目的は、「痛みを取ること」よりも「バランスを取り戻すこと」にあります。 気血水の巡りを整え、陰陽の偏りを修正することで、自然と頭痛の頻度や強さが減っていきます。 多くの方が、頭痛が軽くなると同時に、睡眠の質が向上し、心が穏やかになると感じています。
6. 日常でできる東洋医学的セルフケア
- 頭が重いときは、百会を軽く押さえながら深呼吸を3回
- 湯船にゆっくり浸かり、肩から首を温める
- 甘いもの・冷たい飲み物を控え、温かい白湯を摂る
- 夜更かしを避け、22時〜23時に就寝(肝・胆の修復時間)
- スマートフォンやPCの使用を1時間ごとに休憩
鍼灸による頭痛治療は、「原因を鎮め、再発を防ぐ」ことを目的としています。 一時的な痛みの抑制ではなく、身体が本来持つリズムを取り戻すことで、 天候やストレスに左右されない、穏やかな日常を取り戻すお手伝いをいたします。