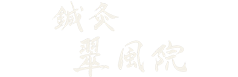「お疲れ様です」「疲れた〜」が口癖になっていませんか?日本人にとって身近なこの感覚ですが、そもそも「疲労」とは何でしょう。ここでは公的情報を参考にしながら、鍼灸師である私たちの視点も交えて、日常で活かせる疲労との付き合い方をやさしく整理します。
1.疲労は「限界」のサイン
過度な活動やストレスが続くと、私たちは「そろそろ休もう」という脳からの合図として疲れを感じます。十分な休息や睡眠が健康に重要であることは、厚生労働省の資料でも繰り返し示されています。[公的資料1] [公的資料2]
- 睡眠や生活習慣の見直しで改善する疲れもあれば、長く続く場合は医療機関の受診が推奨されます。[公的資料1]
- 疲労は非常に一般的な自覚症状で、米国の公的健康情報でも生活要因から疾患まで幅広い背景が説明されています。[公的情報3]
※強い疲労が数週間以上続く、日常生活に支障が出る、あるいは他の症状(息切れ・動悸・発熱・体重減少等)を伴う場合は、早めの受診を検討してください。[公的情報3]
2.東洋の知恵に学ぶ「疲れのタイプ」
東洋の考え方では、同じ「疲れ」でも人によって原因や現れ方が異なると捉えます。ここでは日常の手がかりとして、行動のヒントを2つに分けて紹介します(医療的な診断ではありません)。
- 動くとスッキリする疲れ:家でじっと休むより、軽い運動や入浴、適切な光を浴びるほうが整うことがあります。[公的資料4]
- 安静が一番の疲れ:とにかく無理をせず、睡眠環境や生活リズムを整えることが助けになります。[公的資料1]
どちらに当てはまるかは日によっても変わります。「自分に合う休み方」を観察して見つけることが第一歩です。
3.鍼灸翠風院が大切にしていること(一般的な情報)
疲労は、からだが「バランスを取り戻したい」と知らせるサインだと私たちは考えます。当院では次のような方針を大切にしています。
- お体の状態を丁寧に把握:生活リズムや休み方の傾向を一緒に確認します。
- 心地よい環境づくり:リラックスしやすい静かな時間・空間を整えます。
- 本来の回復力を尊重:無理を重ねない過ごし方の工夫を提案します。
※鍼灸は医療上の診断や標準治療の代替ではありません。症状が続く/悪化する場合や基礎疾患が疑われる場合は、まず医療機関で評価を受けることを推奨します。
4.「疲れが続く」場合に知っておきたいこと
長引く・説明のつかない強い疲労については、国際機関でも情報が提供されています。定義や診断には現時点で合意が十分でない点もあることが示されています。[国際機関情報] 気になる場合は、自己判断を避け、専門の医療機関に相談しましょう。
5.まとめ
- 「疲れ」は休息や生活習慣の見直しを促すサイン。
- 合う休み方は人それぞれ。軽い運動・入浴・光の活用や睡眠環境の調整など、できる範囲から。
- 長く続く・強い疲れは医療機関で評価を。
- 鍼灸はリラクゼーションや日々のセルフケアを補助する選択肢のひとつとして活用する方もいます(治療の代替ではありません)。
ご予約・ご相談
「休んでも抜けない」「休み方がわからない」と感じる方へ。初回は生活背景や休息のとり方も含めて丁寧に伺い、無理のないセルフケアをご一緒に考えます。
- 🟩 徳島院:毎週火曜 9:00–20:00
- 🟦 神戸三宮院:月・水・金・土(祝休)
- LINE:@156asmes