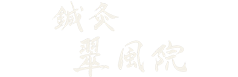【症例集】腰痛
- HOME
- 【症例集】腰痛
三宮 腰痛 鍼灸|神戸の鍼灸 翠風院 症例と東洋医学的解説
三宮 腰痛 鍼灸・神戸 腰痛 改善・東洋医学・自律神経・ギックリ腰・仙骨痛・脊柱バランス
長引く腰の痛みやギックリ腰、整形外科で「異常なし」と言われた痛みは、東洋医学では「気血の滞り」「腎の弱り」「冷え」による不調と考えます。 鍼灸 翠風院では、身体の根から整え、再発しにくい健やかな状態を目指します。
腰痛とは ― 西洋医学と東洋医学の両面から
西洋医学では腰痛の約85%が原因不明とされ、筋肉や関節、椎間板の軽度損傷やストレスによる神経過敏などが関与します。 神経性疼痛・椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症など、MRIで異常が見られるケースもありますが、多くは「姿勢・冷え・精神的緊張」によって悪化します。
東洋医学では「腰は腎の府」とされ、腎のエネルギーが不足すると腰が支えられなくなると考えます。 また、「気血の滞り」「寒湿(冷え)」も痛みの主な原因です。 痛みを抑えるだけでなく、なぜその部位に痛みが生じるかを探り、体質全体から整えていくのが鍼灸の特徴です。
腰痛の基礎医学情報:日本整形外科学会「腰痛について」
実際の症例紹介
【症例1:40代女性/交通事故後の仙骨痛】
主訴:交通事故後の腰痛(仙骨部)
現病歴:半年前の追突事故以来、仙骨周囲に強い痛み。動くたびに激痛が走り、家事も困難。整形外科・接骨院で治療するも改善せず来院。
施術経過:東洋医学では「腰は腎の府」とされ、仙骨は腎の経絡と深く関係します。 腎兪・志室・百会などを中心に施灸と軽鍼を行い、全体の気の巡りを整える施術を重ねました。 5回目でペインスケール10→3~4へ軽減、10回目で痛みはほぼ消失。 現在は体調管理のため月1〜2回通院中。

【症例2:40代女性/ギックリ腰(急性腰痛)】
主訴:ギックリ腰による腰部激痛
現病歴:数日前より起床時に激痛出現。前屈動作で強く痛み、靴下を履くのも困難。 既往にギックリ腰数回あり。睡眠不足と仕事のストレス、冷え込みが重なって発症。
東洋医学的判断:腎虚と肝気上逆が主因。冷えと疲労で腎が弱り、肝気が上昇して筋緊張を起こした状態と診立て。
施術経過:百会に20分置鍼し、肝気の高ぶりを鎮める施術。 施術後すぐに起き上がれるようになり、痛みは10→2に軽減。 翌日から日常生活動作が可能となりました。

※上記症例は施術の一例であり、すべての方に同様の効果を保証するものではありません。 症状や体質、生活習慣によって経過は異なります。
ご予約・ご相談はこちらから
腰痛やギックリ腰でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談はLINEで受付中。完全予約制で、静かな個室空間で施術を行っています。
腰痛と東洋医学 ― 深い理解と整え方
東洋医学では、腰痛を単なる「筋肉の痛み」や「骨格の歪み」として捉えません。 身体の内側で起こる気血の乱れ、内臓の働きの偏り、そして心身の緊張状態が絡み合って、結果として“腰に現れる”と考えます。 つまり腰の痛みは、「身体全体の声」であり、局所治療だけでは真の解決に至らないことが多いのです。
1. 腎(じん)と腰 ― 生命力の源との関係
東洋医学では「腎は精を蔵し、腰は腎の府」といわれます。 腎は生命力の根を司り、成長・老化・ホルモン・骨・耳・髪などにも深く関わる臓です。 腎の働きが弱ると、腰の支えが失われ、慢性的な痛みやだるさ、冷え、下半身の力不足といった症状が出やすくなります。 年齢を重ねることで“腎虚”になりやすく、そこに冷えや疲労、睡眠不足が重なると腰痛が慢性化していきます。
鍼灸では、腎兪・志室・命門などの経穴を中心に、身体の中心軸に温かいエネルギーを巡らせるように整えます。 これにより腰だけでなく、体全体に安定感が戻り、「足腰に力が入るようになった」「姿勢が自然に起きる」と感じる方も多いのです。
2. 気血の巡り ― 痛みを生む滞りをほどく
東洋医学では、痛みの多くを「不通則痛(とおらざればすなわち痛む)」と表現します。 これは、気(エネルギー)と血(血液)の流れが滞ると、そこに炎症や緊張、しびれが生じるという意味です。 長時間のデスクワーク、精神的ストレス、冷え、外傷などはこの“滞り”を作ります。 その状態が続くと、血の質も粘り、筋肉が硬くなり、結果として慢性的な腰痛へと移行します。
鍼灸では、滞った流れを少しずつほどくように、 深部の気血循環を促しながら、痛みの原因となる「結(しこり)」を自然に緩めていきます。 その過程で血流が改善し、体が温まり、呼吸が深くなり、痛みが軽くなると同時に眠りの質も向上していきます。
3. 冷えと湿 ― 天候や環境に影響される腰痛
梅雨時や冬場に腰が重くなる方は、「寒湿(かんしつ)」と呼ばれる体質傾向があります。 体の冷えや湿気が経絡を塞ぎ、血流を妨げることで、鈍い痛みや重だるさを感じやすくなるのです。 特に冷房の効いたオフィスや、薄着・冷たい飲食物の摂りすぎも腰痛の要因となります。 「冷え」は腰痛だけでなく、月経痛・むくみ・倦怠感にもつながります。
鍼灸では、温かい灸や遠赤外線の熱を用い、 腎兪・命門・足三里・三陰交などを中心に体を芯から温める施術を行います。 体温が上がることで免疫力・代謝が高まり、血の巡りも自然に整っていきます。
4. 肝(かん)とストレス ― 精神状態が腰に与える影響
意外に思われるかもしれませんが、ストレス性の腰痛は非常に多いです。 東洋医学では、ストレスや感情の抑圧によって「肝気(かんき)」が滞ると、筋肉(筋=肝の支配部位)が緊張しやすくなると考えます。 イライラ・緊張・不安が続くと背中や腰の筋肉が硬直し、血流障害を起こし痛みへとつながるのです。
このタイプの腰痛では、百会・太衝・内関など、心身をゆるめるツボを使い、 深呼吸が自然にできる状態へ導いていきます。 「気持ちが落ち着いたら腰の痛みも和らいだ」というケースも多く、 心と体を切り離さずに整えることが、東洋医学の特徴です。
5. 全身のバランスからみる腰痛の治し方
腰痛は、局所だけをみていては根本的な解決に至りません。 東洋医学では、「上虚下実」「気逆」「中焦不調」など、全身のバランスを観ながら施術の方針を立てます。 たとえば、胃腸が弱って腰痛が起こるケース、冷え性で下半身の血流が滞るケース、 あるいは呼吸が浅く体幹が支えられないケースなど、原因は人によってさまざまです。
そのため翠風院では、初診時に脈・舌・腹を丁寧に診て、 痛みの背景にある体質・生活習慣・気の流れを総合的に読み取り、 「なぜ今、腰が訴えているのか」を共に探ります。 それに基づき、最小限の鍼と温灸を用いて、身体が自ら整う力を静かに引き出します。
6. 日常でできる東洋医学的セルフケア
鍼灸施術と合わせて、日々の暮らしの中でも腰を守る方法があります。 温める・休める・緊張を抜く――この3つを基本とし、 以下のようなセルフケアを続けることで、痛みの再発を防ぐことができます。
- 寝る前に下腹部や腰に湯たんぽをあてて温める
- 深呼吸をゆっくり5回、胸郭と腹を同時に動かす
- 甘いもの・冷たい飲み物を控え、温かいスープや白湯を摂る
- ストレスが強い日は、百会や合谷を軽くマッサージ
このように東洋医学は、腰痛を「結果」ではなく「状態の表現」として捉えます。 症状の奥にある体質を整えることができれば、 痛みのない時間が増え、心身の調和が自然に取り戻されていきます。 鍼灸はその“きっかけ”を与える静かな医療です。