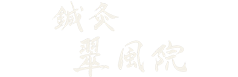2025/05/16
鍼灸 翠風院の橋本です。
思いつきですが、日々学んだことを記すためブログを書いていこうと思います。
今回は引きこもりについて。
鍼灸院には思春期の小学生~高校生で、起立性調節障害や過敏性腸症候群、発達障害などで学校に行けなくなってしまい、
そちらの治療で来られる方はいますが、大人の方で直接引きこもりの改善を求めて来院される方は滅多にありません。(というより今まで経験がないです)
初めは心療内科や精神科、カウンセラーなどに行くでしょう。(本人が嫌がって行かないパターンも多いかもしれませんが)
しかし当院に来られている患者さんや患者さんの親戚、知り合いに引きこもりの方がいることはそれなりにあります。
私自身、高校1年生の時に過敏性腸症候群になり、学校に行けなくなり退学。
そこからしばらく1年以上は引きこもりの状態を経験しました。
そしてそのような人と関わるようになり、少しですが勉強して納得したところがありますので共有としてブログを書きました。
最後まで読んでいただけると嬉しいです(‘ω’)
参考図書 春日武彦著「援助者必携 はじめての精神科第3版」 医学書院
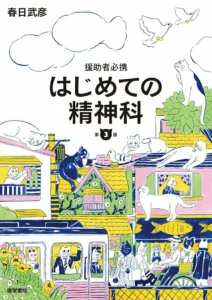
こちらの本には引きこもりには3つの種類があるとされています。
ひとつは「統合失調症」
もうひとつは「思春期の挫折」
3つ目は「発達障害」とされています。(重なる場合もあります)
以外と見落とされやすいのが「統合失調症」による引きこもりだそうです。
統合失調症についてもこの本に紹介されていますが、急性期は幻聴や被害妄想などがあり、こちらは投薬治療で効果が現れやすいものですが、
慢性期になると
「(1)表情が乏しくなる
(2)ある種のルーズさや無頓着さ。さらには感覚的なバランスの悪さ
(3)鈍感さと過敏さとの同居
(4)連想における飛躍傾向
(5)エネルギー水準の低下
何もしていなくとも、彼らは生きているだけ、存在しているだけで疲れてしまう。
(6)気がきかない、理屈は合っているが非現実的、空気を読めない
(7)仕事の覚えが悪い、経験を生かせない、融通がきかない 」
などが見られるようになります。
一見うつ病に見えるケースもあるそうです。
統合失調症は現代医学においては投薬で体調を管理するというのがスタンダードですね。
東洋医学、鍼灸においては統合失調症はアプローチ出来る疾患で、師匠の藤本蓮風先生も多くの統合失調症の方を診て来られました。
統合失調症は完全に治るものではありませんが、薬や鍼灸、漢方においてコントロール出来れば、引きこもりから脱出し、社会的生活を送ることは可能と思います。
次は「思春期の挫折」
私が引きこもったのはこちらに当てはまるでしょうね。
具体的にいうと、当時それなりに勉強していたので医学部を目指し予備校に通い始めましたが、内容がハイレベルでついていけず、それを親に言わずに予備校をよく休んでいました。
他にもストレスはありましたが、今まで頑張って来たこと(勉強)がなかったことのようにわからなくなり、それが一番の原因で過敏性腸症候群から引きこもりになったと思います。
今思えば親からのプレッシャーもあったと感じます笑
わかりやすい挫折ですね。
そこから一日中ゲームして過ごすようになり、1週間、1カ月、半年とドンドン月日は流れていきます。
間で通信教育の学校に行こうと親が手配してくれましたが、嫌すぎて結局いきませんでした。
この時は18才(高校卒業時)になったら大学か専門学校にいかないと行けないなと感じながらも日々ゲームやドラマ楽しいーー!!って感じで過ごしていたと思います。
その後父の治療(鍼灸師)とお散歩を頑張った結果、過敏性腸症候群が改善。将来を考えた時に鍼灸師もいいなーと思い、鍼灸大学に入学し現在に至ります。
といった感じで挫折はありつつも、わかりやすい期限があったので引きこもりから脱することが出来たという形ですね。
子供の引きこもりは中学入学、高校入学、大学or専門学校入学といった節目があるため、比較的脱しやすいと思います。(このタイミングを逃すと難しいかもしれません)
で問題なのは社会人の年齢になってから。
そのような方はどのような内面か以下本文より引用します。
「本当は、ひきこもっている場合ではない。さっさと社会に戻って、苦しい現実と向き合わなければいけない。駄目な自分、思っていたほど優秀ではなかった自分を
受け入れなければならない。・・・ぐずぐず逡巡しているうちに、自己嫌悪がつのってくる。・・・本人は罪悪感を強く覚えている。でも、どうしようもない。今さらどうがんばれば
よいかすら分からない。」
「扉の内側で時間をフリーズさせ、そのことによって自己嫌悪や罪悪感の生々しさから逃れようという矛盾に陥っているのです。」と
ではどうすればよいか。本には目標をひきこもりの終了ではなく、親との和解を目指すべきとあります。
私の例では、始めは我が儘にやりたい放題(朝4時までゲームなど)してよく親とぶつかっていました。ネット回線切られたこともあります笑
しかし徐々に親子関係も改善していったため、大学も無事にいけたと感じる面もあります。
和解することで自己嫌悪や罪悪感がやわらぐということですね。
また本に実例が載っていて非常に参考になります。
詳しく書くと長いので、まとめますと
長年引きこもる娘と母がいて、悶々とした日々を両者送っていました。
しかし娘のことを心配しても、心配したぶんだけ何かが起こるわけでもない。それじゃあ自分なりに自分の幸せを追求しようと思い、
山歩きを始めた。すると生き生きするようになり、心の余裕が生まれ親子関係が改善したとあります。
これはとても重要なことと思いました。
親(特に母)は子供のことが心配で、他のことを差し置いてでも頭の中は常に考えてしまうことがあります。
当然と言えば当然ですが、適度に距離を保ち、心に余裕を持つと接し方も変わり、罪悪感を減らしていけるという一見無慈悲に見える行動こそ、もっとも慈悲ある行動なわけですね。
といろいろ長くなったので、今回のブログはここまで。
発達障害の引きこもりは本を読むか私に直接聞いてください笑
こんな感じで時々アップします(;’∀’)
思いつきですが、日々学んだことを記すためブログを書いていこうと思います。
今回は引きこもりについて。
鍼灸院には思春期の小学生~高校生で、起立性調節障害や過敏性腸症候群、発達障害などで学校に行けなくなってしまい、
そちらの治療で来られる方はいますが、大人の方で直接引きこもりの改善を求めて来院される方は滅多にありません。(というより今まで経験がないです)
初めは心療内科や精神科、カウンセラーなどに行くでしょう。(本人が嫌がって行かないパターンも多いかもしれませんが)
しかし当院に来られている患者さんや患者さんの親戚、知り合いに引きこもりの方がいることはそれなりにあります。
私自身、高校1年生の時に過敏性腸症候群になり、学校に行けなくなり退学。
そこからしばらく1年以上は引きこもりの状態を経験しました。
そしてそのような人と関わるようになり、少しですが勉強して納得したところがありますので共有としてブログを書きました。
最後まで読んでいただけると嬉しいです(‘ω’)
参考図書 春日武彦著「援助者必携 はじめての精神科第3版」 医学書院
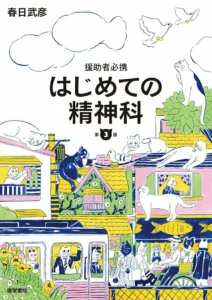
こちらの本には引きこもりには3つの種類があるとされています。
ひとつは「統合失調症」
もうひとつは「思春期の挫折」
3つ目は「発達障害」とされています。(重なる場合もあります)
以外と見落とされやすいのが「統合失調症」による引きこもりだそうです。
統合失調症についてもこの本に紹介されていますが、急性期は幻聴や被害妄想などがあり、こちらは投薬治療で効果が現れやすいものですが、
慢性期になると
「(1)表情が乏しくなる
(2)ある種のルーズさや無頓着さ。さらには感覚的なバランスの悪さ
(3)鈍感さと過敏さとの同居
(4)連想における飛躍傾向
(5)エネルギー水準の低下
何もしていなくとも、彼らは生きているだけ、存在しているだけで疲れてしまう。
(6)気がきかない、理屈は合っているが非現実的、空気を読めない
(7)仕事の覚えが悪い、経験を生かせない、融通がきかない 」
などが見られるようになります。
一見うつ病に見えるケースもあるそうです。
統合失調症は現代医学においては投薬で体調を管理するというのがスタンダードですね。
東洋医学、鍼灸においては統合失調症はアプローチ出来る疾患で、師匠の藤本蓮風先生も多くの統合失調症の方を診て来られました。
統合失調症は完全に治るものではありませんが、薬や鍼灸、漢方においてコントロール出来れば、引きこもりから脱出し、社会的生活を送ることは可能と思います。
次は「思春期の挫折」
私が引きこもったのはこちらに当てはまるでしょうね。
具体的にいうと、当時それなりに勉強していたので医学部を目指し予備校に通い始めましたが、内容がハイレベルでついていけず、それを親に言わずに予備校をよく休んでいました。
他にもストレスはありましたが、今まで頑張って来たこと(勉強)がなかったことのようにわからなくなり、それが一番の原因で過敏性腸症候群から引きこもりになったと思います。
今思えば親からのプレッシャーもあったと感じます笑
わかりやすい挫折ですね。
そこから一日中ゲームして過ごすようになり、1週間、1カ月、半年とドンドン月日は流れていきます。
間で通信教育の学校に行こうと親が手配してくれましたが、嫌すぎて結局いきませんでした。
この時は18才(高校卒業時)になったら大学か専門学校にいかないと行けないなと感じながらも日々ゲームやドラマ楽しいーー!!って感じで過ごしていたと思います。
その後父の治療(鍼灸師)とお散歩を頑張った結果、過敏性腸症候群が改善。将来を考えた時に鍼灸師もいいなーと思い、鍼灸大学に入学し現在に至ります。
といった感じで挫折はありつつも、わかりやすい期限があったので引きこもりから脱することが出来たという形ですね。
子供の引きこもりは中学入学、高校入学、大学or専門学校入学といった節目があるため、比較的脱しやすいと思います。(このタイミングを逃すと難しいかもしれません)
で問題なのは社会人の年齢になってから。
そのような方はどのような内面か以下本文より引用します。
「本当は、ひきこもっている場合ではない。さっさと社会に戻って、苦しい現実と向き合わなければいけない。駄目な自分、思っていたほど優秀ではなかった自分を
受け入れなければならない。・・・ぐずぐず逡巡しているうちに、自己嫌悪がつのってくる。・・・本人は罪悪感を強く覚えている。でも、どうしようもない。今さらどうがんばれば
よいかすら分からない。」
「扉の内側で時間をフリーズさせ、そのことによって自己嫌悪や罪悪感の生々しさから逃れようという矛盾に陥っているのです。」と
ではどうすればよいか。本には目標をひきこもりの終了ではなく、親との和解を目指すべきとあります。
私の例では、始めは我が儘にやりたい放題(朝4時までゲームなど)してよく親とぶつかっていました。ネット回線切られたこともあります笑
しかし徐々に親子関係も改善していったため、大学も無事にいけたと感じる面もあります。
和解することで自己嫌悪や罪悪感がやわらぐということですね。
また本に実例が載っていて非常に参考になります。
詳しく書くと長いので、まとめますと
長年引きこもる娘と母がいて、悶々とした日々を両者送っていました。
しかし娘のことを心配しても、心配したぶんだけ何かが起こるわけでもない。それじゃあ自分なりに自分の幸せを追求しようと思い、
山歩きを始めた。すると生き生きするようになり、心の余裕が生まれ親子関係が改善したとあります。
これはとても重要なことと思いました。
親(特に母)は子供のことが心配で、他のことを差し置いてでも頭の中は常に考えてしまうことがあります。
当然と言えば当然ですが、適度に距離を保ち、心に余裕を持つと接し方も変わり、罪悪感を減らしていけるという一見無慈悲に見える行動こそ、もっとも慈悲ある行動なわけですね。
といろいろ長くなったので、今回のブログはここまで。
発達障害の引きこもりは本を読むか私に直接聞いてください笑
こんな感じで時々アップします(;’∀’)